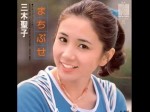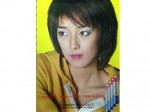祭りと酒と日本人
- 2015/5/10
- 日本酒

スポンサーリンク
祭りと酒と日本人
祭りという言葉の語源は、祀りという言葉である。
祭り
⇒ フェスティバルのような感覚ですね。
祀り
⇒ 神様を慰める儀式を行う事。
私達、現代人が使用する「まつり」という言葉も、元々は神様を祀る事が発祥だったと言われています。
■ 祀りにも、祭りにも、お酒は欠かせないモノ
その昔、まつりの際にはまず神様にお酒を供え、その後、それを民が下げて頂く。
という風習があったようです。
神様と同じモノを頂く事で、神様との親密な関係を願ったと言われています。
ちなみにですが、お酒を神に供え、それを後から頂く儀式を、直会(なおらい)と呼ぶそうです。
このように、古の時代より、私達日本人はお酒を特別な飲み物として、扱ってきた事が容易に想像できますし、おどろく事に、万葉集には祀りとお酒と神様が登場する歌が幾つもあります。
そのことから、お酒は まつり の日に合わせて作られていた。
そう言い伝えられています。
欧米にも、酒をメインにした祭りは多数ありますが、ビール祭りにしても、ワイン祭りにしても、恵みを神様に感謝する為の行為。
そんなテーマ性の物である事とは違い、日本酒は、元来、人が飲む為に作られた訳ではなく、神様が飲む為の物であった。
どうやら、こういう事らしいのです。
では、現代の祭りでのお酒の立場をみてみましょう。
◎純粋に祭りを楽しむ為にお酒を嗜む
ほろ酔い気分で多少ハメを外す?(笑)
そんな光景を毎年のように見ますが、踊る阿呆に見る阿呆とはよく言ったモノですね。
普段はお堅い人でも、祭りの時ぐらいは、踊る阿呆になる。
その行為をちょっとだけ後押ししてくれる物がお酒なのかもしれません。
純粋に祭りという、特別な日を楽しむ為のアイテムとして、お酒という物が存在しています。
◎清めの儀式、安全祈願として扱われる。
神輿を担がれたり、山車を引いた事がある方はご存じかもしれませんが、お祭りが始まる前に、お神酒で安全祈願をしたりもします。
ここでは、祀りの風習が残っている。
という事になりますね。
祀りという神前の儀式から、現代の祭りという文化に移り変わって行く中でも、「お酒」という物は、相変わらず私達の傍に存在している訳です。
今年の祭りの日は、そんな事を浮かべながら、お酒を嗜み、そこから踊る阿呆になってみてください。
スポンサーリンク